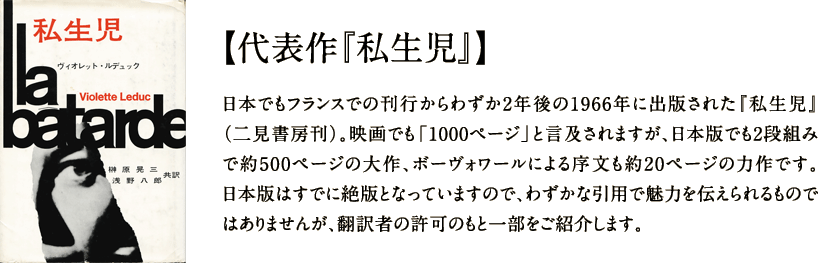
1945年のはじめ、わたしはヴィオレット・ルデュックの原稿をはじめて読んだ。−「母はわたしに片手さえかしてくれようとしなかった」−読みはじめるやいなや、わたしはこの作家が持っている天分と文体にとりつかれてしまった。まもなく、アルベール・カミュがルデュックの作品《窒息》を自分の主宰する《エスポアール叢書》に収録した。それから、ジュネと、ジュアンドーと、サルトルとが、新しく現れたこの作家に敬意を表した。ルデュックの才能は、続いて発表した諸作品によって、確乎たるものになった。きびしい批評家たちも、彼女の才能を高く評価した。ところが一般の読者には気にいらなかった。だから多くの識者たちの称賛を集めながらも、これまでヴィオレット・ルデュックは世に知られていなかったのである。
(略)
ヴィオレット・ルデュックは読者によろこばれようとしない。よろこばれようとしないどころか、恐怖さえいだかせる。彼女が書いた作品の題名−たとえば《窒息》《飢えた女》《荒廃》−からして、感じのいいものではない。ひとたびそれらの作品をひもとくと、読者は騒音と恐怖にみちた世界をかいま見る。その世界の中では、愛が憎しみの名前を持っていることがよくある。生への情熱が絶望の叫び声をまきちらしている。それは孤独のために荒廃した世界であり、遠くから見れば、およそうるおいのないように見える。しかし、ほんとうはそうではない。
「わたしはひとりごとをいう砂漠です」
いつかヴィオレット・ルデュックが、こんなことをわたしに書いてよこした。ところが、わたしはこの砂漠の中で、数限りない美しいものに出会った。孤独の底からわれわれに語りかけてくるひとはみな、ほかならぬわれわれ自身を語ってくれているものだ。
(略)
ヴィオレット・ルデュックの本は〝涙と叫び声〟に充ちてはいるが、「食欲を増進させる」。−彼女はこの言葉が好きだ。その理由として、わたしは悪に犯されても失わない彼女の純潔のせいだといいたい。また、これらの本が闇の中から数多くの豊かさを奪い取っているせいだといいたい。
(略)
《私生児》は、この本の初めで語られている作者の幼女時代の話が語り終えられた瞬間、《私生児》ではなくなった。こうして環がしめくくられる。他者との関係に失敗したものは、この特権的な形式を持つ伝達形式−すなわち、ひとつの文学作品に到達したのである。
(略)
わたしの境遇は、たいしてめずらしいものではない。わたしは死ぬのがこわい。この世に生きていることをなげき悲しんでいる。今までわたしは、働いたことはないし、学問もない。わたしはずっと泣いてきた。泣き叫んできた。長いあいだ、涙と泣き声がわたしに取りついてはなれなかった。そんなことを考えるととたんに、失われた時間が責苦となってのしかかってくる。わたしはひとつのことを長いあいだ考えているなんてことはできない。反省するなんていうこともできないのである。しおれたサラダ菜の葉に満足できる女なのだ。過去は滋養にはならない。わたしは今まで生きてきたように、これからも生きていくだろう。これまでわたしを責めさいなんできたあやまちを、そのまま背負い込んでいくだろう。今度生まれてくるなら、彫像に生まれてくればいいと思う。堆肥の下にうごめくなめくじに生まれればいいと思う。美徳、特性、勇気、瞑想、教養、わたしは手をつかねたまま、そんな言葉におしつぶされてしまいそうだ。
(略)
おかあさん、老人のあなたが時計のような正確さでむかしのことを思い出すとき、あなたはわたしの子供に戻ってしまうのです。あなたが話し出すとはじめて、あなただと、気がつくのです。あなたが話すとあなたのことを脳裏に浮かべるのです。そうです、あなたにはわたしのお腹が火山のような熱気を持っているように思えるのでしょう。あなたがしゃべるとわたしはだまってしまいます。わたしはあなたの不幸を背負いこんで生まれてきたのです。ひとが神への供物を背負って生まれてくるようにね。あなたは、人が生きるためには過去の中に生きなければならないことを知っていました。
ときどき、わたしはそんな過去につかれはてて、病気になってしまうこともありました。また真夜中に、わたしがベッドにはいっていて、あなたが肘かけ椅子にもたれているとき、あなたはこういったものでした。
「わたしはあの男しか愛さなかったのよ。それもたった一度しか愛さなかったのにおまえが生まれてしまったんだよ」
わたしはあなたのほこりをかむった髪のために、竪琴となり、ヴィブラフォーンとなります。あなたは年老いて身よりもありません。わたしがボンボン入れのふたを取ると、あなたはこういいました。
「おまえ、眠っちゃったのかい? もう目をつむっちゃっているんだね」
わたしは眠ったのではありませんでした。あなたの老いのくりごとからにげ出したかっただけでした。わたしは髪の毛をクリップでとめていました。自分の指を見ていると、二十五歳ころのあなたを、そのころのあなたの青い目を、黒髪を、形のきれいなレースを、胸飾りを、ヴェールを、大きな帽子を思い出します。そして同時に、五歳だったわたしの苦しみを思い出します。わたしの優雅なひと、しわもよっていないひと。けなげな女、敗れた女、耄碌した女、わたしを消す消しゴム、わたしの嫉妬、正義、指揮官、小心者。おかあさん、これがみんなあなたの姿なのです。
(略)
私生児 フランス版:1964年ガリマール社より初版刊行 日本版:1966年7月25日、二見書房より初版刊行 榊原晃三/浅野八郎訳